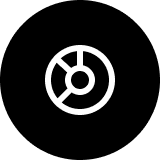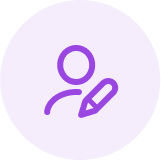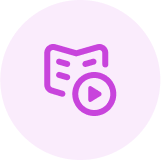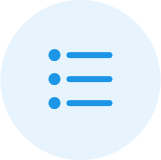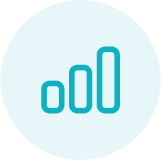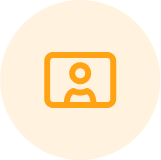アドビリソースセンター
エンタープライズ向けのマーケティングリソース、ビデオ、ウェビナーなど。製品、業種、タイプ別に、ビジネス目標に合わせたコンテンツを見つけましょう。

cover


2026年のマーケティング:Experience Makersが描く新たな時代の顧客体験
変化の大きい市場状況の中で、企業のマーケティングはどうあるべきか。最先端の取り組みを進めるExperience Makerの方々に展望を伺いました。

cover


成長を加速させる:AIでコンテンツを成長のエンジンに
AIを活用してコンテンツを本質的なビジネス価値に変える方法(平均7倍のROI)と、各業界での価値のあるユースケースを学びましょう。
リソースを検索(製品別)
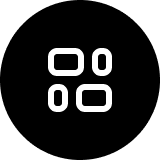
Experience Manager Assets

Experience Manager Sites
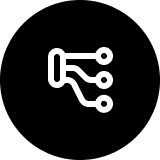
Journey Optimizer